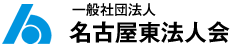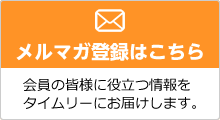歴史講演会『光る君へ』の見どころを探る!


今年の歴史講演会は、大河ドラマ『光る君へ』の見どころについて、様々な視点からお話を致しました。
これまでの大河ドラマでも、平安時代を舞台として取り上げられることは少なく、尚且つその殆どが武士を中心に描かれていて、王朝貴族目線のドラマという斬新な設定に新鮮味を感じる一方で、馴染みが薄くてよくわからないと思われた方も多いと思われます。今回の講演では、その様な事情を考慮に入れ、平安時代の政治・社会の仕組みを簡単に説明する所から始めました。
社会の頂点に立つ帝(天皇)を官人(今でいう公務員)が補佐して政治を行なうのですが、その運営を担うのは五位以上の位を持つ貴族であり、更に三位までの上級貴族とされる一握りの公卿達が政治の意思決定に参画していました。
平安時代も中期に入ると、藤原氏の勢力が他氏を大きく凌駕する様になっており、彼等は帝の私的空間である後宮に一族の娘を入内させて、その出生の皇子を皇太子、更には即位させることにより、自らは外戚として政治の実権を掌握するという、新たな政治システム(摂関政治)を構築・軌道に乗せていました。
外戚を藤原氏が独占されるに至ってからは、次はその座を巡っての一族又は家同士の争いへと移り、熾烈な権力抗争が展開された結果、覇権を握ったのは、藤原道長の父である兼家でした。
兼家死後は息子達(同母兄弟)の争いとなったのですが、末弟であった道長は、長兄・次兄の相次ぐ死没、当時の帝の生母であった姉の支援、更には強力な対抗馬であった甥との争いに勝利!多くの幸運に浴した結果、政治の頂に立つことになります。
但し、道長の苦闘は寧ろここからが本番で、娘を帝の後宮に入内させることには成功したものの、なかなか皇子を儲けることは叶わず、甥でもある帝との協調関係を維持しつつも時として緊迫した局面を生じさせていたのです。
『亡き后の面影を忘れられない帝の心を、何とかして娘に向けることは出来ないものか?』思案に暮れた道長が考えついたのは、文学好きの帝が興味を持つ物語を書く女性を娘の女官(女房)として採用することでした。道長から白羽の矢を立てられたのが、この時代の代表的な女流作家である紫式部であり、彼女が著した物語こそが、『源氏物語』だったのです。
平安中期を政治と文学の分野で牽引する存在であった道長と式部のコラボが…
果たしてどの様な相乗効果を生み出すのか?
時間の都合でお話はそこまでになってしまったのですが、あまり知られていなかった時代や、そこで躍動した人物、更にはその時代の貴重な史料である『日記』や物語等に興味を持って頂けたならば、望外の喜びであります。ありがとうございました。
(タケ海舟こと小川剛史)